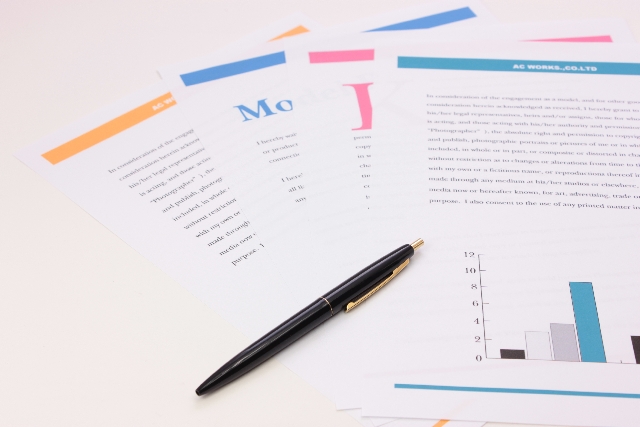


失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。
そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。
採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。
でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・
※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります
-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。
逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。
給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。
採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。
でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・
※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります
-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。
逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。
給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
引越→入籍までの間の手続きについて
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更
以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。
何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?
果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・
★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?
アドバイス、お願いしますm(_ _)m
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更
以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。
何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?
果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・
★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?
アドバイス、お願いしますm(_ _)m
ここで質問しても、住民異動届は居住実態に合わせてしてください。運転免許証の記載事項変更は「速やかに」してください、としか回答できません。
住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。
婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。
補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。
婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。
その他、住所変更で必要になりそうなもの
印鑑登録、郵便局・宅急便へ転居届、電気、ガス、水道、クレジットカード、証券会社、保険会社、携帯、ネット、NHK、CS、新聞、定期購読の雑誌、ネットショップ、JAF、、、
住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。
婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。
補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。
婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。
その他、住所変更で必要になりそうなもの
印鑑登録、郵便局・宅急便へ転居届、電気、ガス、水道、クレジットカード、証券会社、保険会社、携帯、ネット、NHK、CS、新聞、定期購読の雑誌、ネットショップ、JAF、、、
会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中
質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)
生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。
個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中
質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)
生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。
個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
①給付対象になり得ません、離職後1年間が受給期限だからです。②一昨年に立ち上がった「基金訓練」というものがあり、世帯収入等の審査がありますが、対象になれば無料で受講でき月当たり10万乃至12万の給付金が受けられます(3か月訓練なら30万)但し、定員の関係もあるので希望者が多ければあぶれることもある為、必ず受講できるとは限りません。③以前からあった教育訓練給付制度というものがあり、受講費用の20%が修了後に申請することによって返戻されますが、雇用保険に加入していて離職後確か1年以内に受講開始した場合に限り適用になるものだと記憶しています。いずれにせよ、これは貴方はあてはまらないかと思います。
失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。
この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
会社を「懲戒解雇」された場合の失業保険は?
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
懲戒解雇は自己都合と同様な感じになり、給付制限が3ヶ月つきます。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
関連する情報